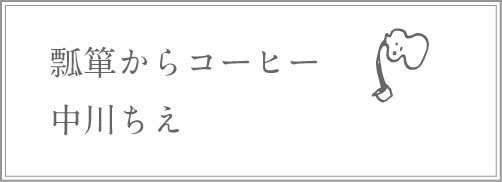
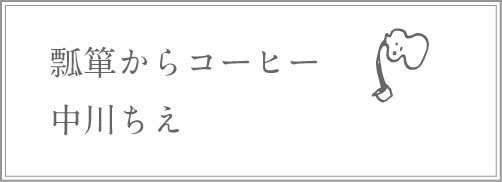 |
□ ミ ッ ク ス ジ ュ ー ス
前回に引き続き今回も喫茶店のお話。
しかもコーヒーのお話ではないのですが…。
好みの喫茶店ってどんなだろう?
私の場合、そのお店の扉を開けた瞬間に
「あっ好きだな、この感じ」という感覚的な事がほとんどで、
食べものや飲みものの味は実は二の次になっている。
でも不思議とそのへんに大きなズレはなく、
大抵好きな感じと味は重なっていることが多い。
そりゃぁ今までにがっかりすることもあったけれど、
最近は動物の勘?食いしん坊の勘?がセンサーのように
働いて、有り難いことにそんなお店と出会える機会が増えている。
大阪の道頓堀近くに「8」(エイト)という
フルーツジュース専門の喫茶店があった。
メニューは旬の果物を使ったジュースのみ。
それこそここは扉を開けた瞬間どころか、
扉の前に立ったときから
「あっ好きだな」
と思わせる雰囲気が漂っていた。
店内は4人くらいが座れるカウンター席と
小さなテーブル席がふたつほど。
古いけれどこざっぱりとしていて、
飾り気のあるものといえばカウンター内の壁に飾ってある
褪せたモノクロの写真が数枚と、奥の窓からは見える道頓堀の景色。
必要以上の愛想は無い「いらっしゃい」の声の主は50代くらいの女性。
そんな素っ気なさもひと目で気に入った。
ジュースはカウンターの上に乗った
トレーに並ぶ果物の種類がその日のメニュー。
果物はずらりとなんか並んでいない。
ディスプレイのように3〜4種類の果物たちが数個ずつ。
でもそれらはとびきりピカピカで、選び抜かれた上等品ということは
こちらに見る目がなくてもすぐわかるほどだった。
なんたってそこに並ぶ果物たちが
「美味しいんだから私たち」とでも言っているように
誇らしげに見えるのだ。
ふたりではじめてそのお店を訪れたときは
せっかくだからと違う果物をそれぞれ選んで注文した。
すると女主人に
「同じ果物にしてくれます?」とピシャリ。
小心者たちはたちまちちぢこまり、
「は、はい。ではイチゴで」と答えたきりふたりとも黙り込んだ。
好きだなの勘ははずれてしまったんだろうか…。
そんな思いが頭をよぎる一方で、決して嫌な感じはしていなかった。
女主人はトレーからピカピカのイチゴを数個選ぶと
静かにカットを始めた。
慣れた手つきと流れるような動作は
呼吸をするのと同じで何の違和感もない。
イチゴのジュースを作るからあれをやって、
次はこうして…などという手順すら頭で考えているのではなく
体に擦り込まれているようななめらかさ。
ほんの数分。カットされたイチゴがそこにあること以外は、
先ほどと何ひとつ変わっていないという風に
下ごしらえがひと通り終わったところで女主人が
カウンターから出て上の階に向かって
「お願いします!」と声をかけた。
「???」
ギシっギシっと木が軋む音。
音のする方へ目をやると、
おじいちゃんがヨロヨロと2階から降りてきた。
「ヨ、ヨーダ!?」
そんなこと口が裂けてもそこでは言わなかった。
細面の顔に皺がひとつひとつ深く刻まれていて…
一瞬にしてスターウォーズのヨーダが頭に浮かび、
「ヨーダだ!」と私は心の中で叫んでいた。
まずお店に2階があることも気づいていなかったし、
イチゴをカットしていたのが店主だと思っていたので
目をパチクリさせながらも平静を装った。
ふたりのやりとりを見ていると店主はこのおじいちゃんで、
女主人だと思っていた人が娘さんらしいということがうかがえた。
ヨロヨロと歩いていたはずのおじいちゃんは
カウンターに立つなりスイッチが入ったように
シャンとした。
そうしてまず大きな氷を年季の入ったアイスクラッシャーに
セットするとレバーをぐるぐる回し始めた。
ガリガリガリガリ。
ピシーン。
合間に氷のかけらがこちらに飛んできた。
…けどおじいちゃんはこちらに鋭い目線を向けただけで何も言わない。
「ひぃぃぃぃーーー!」
こわいよぅ!と思っても決して口には出さずに
まだまだ頑張って平静を装った。
氷をかき終えるとおじいちゃんは
いよいよジューサーに材料を入れ始めた。
氷の他に先ほどのイチゴ。
卵黄や生クリーム? 牛乳? ガムシロップ?
やはりおじいちゃんの動作もなめらかで、
何が入っているかは目で追っていてもわからないほど。
というよりも、おじいちゃんの指先が顔の皺とは反比例するように
瑞々しい上に白く、その美しさについ見とれてしまって
なんだかわからなくなってしまったのだ。
あまりにもこちらがじーっと見ているからか、
時々するどい視線が何度かこちらにも向けられ、
その度にドキドキしてしまう。
ようやくグラスにジュースが注がれて、
最後に香りつけなのか、魔法をかけるように
レモンの皮がサッと絞られた。
目の前に差し出されたミックスジュース。
ひと口飲んで「美味しい!」と大きな声で言いたかったけれど
それも憚れるようでジュースと一緒にのみ込んだ。
だって美味しくないわけがないのだから。
仕事が終わるとおじいちゃんはまたヨロヨロとした
足取りでカウンターから出てきた。
ワインレッドのシャツに鶯色のカーディガン。
そんな組み合わせ、なかなか似合う人はいない。
おじいちゃんはかなりの洒落者だ。
若いころはさぞかし男前だったろうと想像してみる。
色褪せたモノクロ写真はフランスかどこか
海外のもののように見えたけれど、
ひょっとしたらおじいちゃんが若い頃…
飲み終えてしまうのが惜しくて惜しくて
ジュースをちびちび飲みながら空想の世界を羽ばたいていた。
「早く飲まないと美味しくなくなってしまいますよ」
またもピシャリ。
慌ててジュースだけに集中してゴクゴクと飲み干した。
「8」は定休日もわからず、3時からやっている日もあれば、
休んでいる日も多かった。
大阪に行く機会がある度に覗いていたけれど、
滞在中に一度も入れなかったときも少なくなかった。
結局はじめて訪れてから2度きり。
小さな看板だけを残していつの間にかお店は閉じられた。
その人にしか出せない味というものがあるのだと思う。
味そのものはもちろん、目には見えない店内の空気もまるごと。
娘さん?が果物のカットしかしなかったのも、
お店が閉じられてしまったのも本当のところはわからないけれど、
そんな理由も少しはあったのかなと勝手に思っている。
黒枠のすりガラスの扉に書かれた「8」の黒い文字。
表の賑やかな通りから小路を入ったつきあたりに位置したそのお店は
入口の灯りで店名の文字がぼわんと浮かびあがっていた。
「あっ好きだな」の感覚は
あの扉の前に立つずっと手前からあったのだ。
|
copyright 2009 anonima studio |