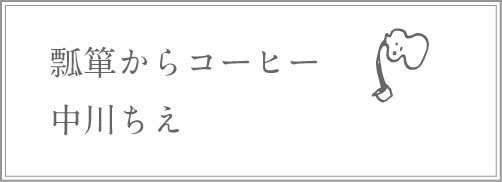
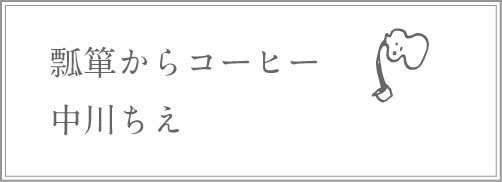 |
□ 言 い わ け の お 土 産
お店のまわりや、自宅の近くで
古いビルや一戸建ての取り壊しを多く見かけるようになった。
地震後の影響が大きいと思うし、色々な事情があるのだろうから
私があれこれ言えた立場ではないのだけれど、
知っている町の姿が変わっていくのはやっぱり寂しい。
勝手な感傷と言われればそれまでなのだけど。
いつも前を通っていたあのお気に入りの建物。
あの壁。あの階段。あの扉。
背の高かったあの木。
そういえばずいぶん行っていないけれど
あの中華料理屋さんはやっているのだろうか。
ううん。きっともう無いだろうな。
女性が夜にひとりで歩くのは少しためらうような歓楽街にあった
おじいさんとおばあさんでやっていたお店。
扉を開けて中へ入ると、エアポケットに入り込んでしまったように
そこだけ嘘みたいに静かだった。
おじいさんもおばあさんも
パリッとアイロンのかかった白い割烹着を着ていたような
気がするけどどうだったろう。うる覚えだ。
お店は古くて、窓は上の方に小さいのがあるくらいで、灯りも少し暗くて。
それでもきっちり磨き込まれて清潔な感じがするお店だった。
それが白の割烹着を思わせているのかもしれない。
とても好きな空気がそこにはあって、
行きたい気持ちはずっとあったというのに、
そこまでの道をとてもひとりでなど歩くことができなくて
ひとりになってからは足が遠のいたままそれっきりになってしまった。
ふたりで行っていた頃は、そこで軽く食事をしている間に
チャーハンをお持ち帰り用に作ってもらって
よく通っていた喫茶店のマスターにお土産で持って行っていた。
チャーハンの具はどんなだったかな。
ごくごくシンプルだったけど、サイコロ状に切った叉焼は確かピンクだったな。
ひとり暮らしのおじいさんマスターは
お料理もしなかったから毎日晩ごはんは
買ってきたものや外食だった。
遠い親戚みたいにしてつきあっていて、
たまにそんな風にして晩ごはんになるようなものを買ったり、
作ったりして持って行っていた。
閉店間際にお土産をぶらさげて、コーヒーを注文しながら
お店の片づけを終えたマスターと一緒に晩ごはんを食べることも度々あった。
お腹がいっぱいのときでも、マスターが美味しそうに食べているのを見ていたら、
自分もついひと口、ふた口と箸が進んでいた。
あのお店のチャーハンはマスターのお気に入りだった。
お店へ向かうときは、ふたりで歩いていても、
ドキドキしながら息を止めるようにうつむいていたけれど、
お店の引き戸をガラガラッと開けて中へ入ると、
そんなことも忘れてホッとしていた。
中華料理屋さんへはマスターを言いわけに。
マスターにはお土産を言いわけにして顔を出していた。
ただ、食べものそのものを食べたいだけなのでも
ただ、コーヒーを飲みたいだけでもないその理由はなんだったのだろう?
言いわけの答えはわかっていたくせに、気づかないふりをしていた。
私がグズグズとそんなことをしているうちに
町の顔は少し変わっていた。

|
copyright 2011 anonima studio |